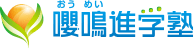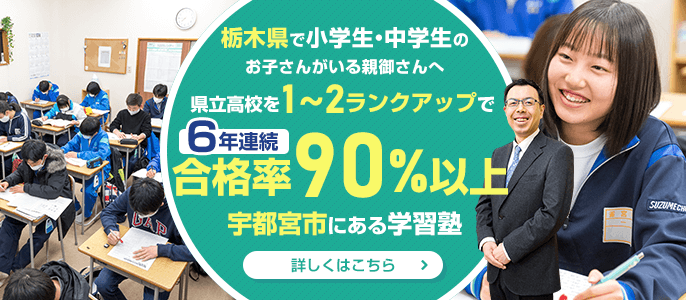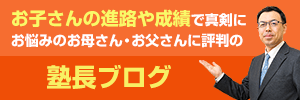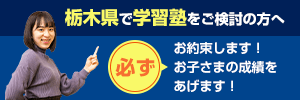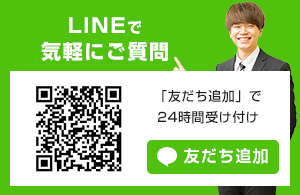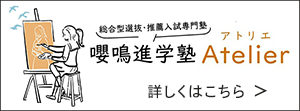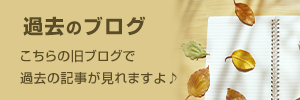後期試験の小論文対策で大逆転合格は可能です!!
こちらのサイトを見てくださっている受験生の皆さん。
前期試験お疲れ様でした。
ほっと一安心という気持ちか、
不安で仕方がないと思っている人など様々だと思います。
もし、不安な気持ちになっている受験生は、
その不安な気持ちを振り払い!
後期試験の勉強は絶対にやった方がいいです!
・後期試験の対策をしたほうが良い理由
周りが勉強できていない時ですので、
しっかりと勉強すれば後期の合格可能性はかなり高まります。
前期で不合格だった大学に後期で受かった人は毎年おります!

逆に全く対策をしなければ受かるものも受からなくなってしまいます。
受験生の皆さんには是非後期まで気を抜かずに頑張ってくださいね。
しかし、具体的にどんな勉強をすればいいか分からないという人もが多いと思います。
たしかに英語や数学といった科目ならやることは前期と変わりませんが、
小論文となると何から手を付ければいいか分かりづらいですよね。
そこで国公立後期試験の具体的な対策方法について紹介していきたいと思います。
・マインドの問題を解決しよう!
まず大切なのが後期試験へと気持ちを切り替えることです!
不安な気持ちも分かります。
やる気が出ない原因は人それぞれだと思います。
前期で燃え尽きたから、
周りが遊んでいるから、
後期の大学に魅力を感じないから……
では!お聞きします。
「キミは後期の勉強をしなくて後悔しないと言い切れますか?!」
私は無理に後期の勉強をしようと言っているわけではありません。
しかし、1つだけ言えることがあるとしたら、
それは勉強しなかったことを後悔することはあっても、
勉強したことを後悔することはないということです!
前期試験で確実に上手くいった自信があっても、
予想外のところでミスを犯しているかもしれません。
今は行きたくないと思っている後期の大学でも、
進学してみたら考えが変わるかもしれません。
未来のことはそのときまで分からないのですから、
どうせなら今できる精一杯!
胸いっぱい!の事をやってみてください。
・小論文対策について
最後に小論文の対策方法についてです。
小論文が課される大学は多いと思います。
特に文系はほとんどが共通テストと小論文といった形ではないでしょうか。
小論文で大事なことは、
当たり前ですが問題の傾向をしっかりと理解することです。
与えられた課題文を要約したうえで
自分の意見を書くという形がオーソドックスですが、
題材となるテーマには多様性があって、
経済学部なら社会・経済系、文学部なら哲学系、理工学部なら自然科学系というように、
その学部で学ぶ内容と関連していることが多いです。
大学に入ってからの勉強にも直接役に立つので、
そうした分野の背景知識はしっかりと押さえておきましょう。
それ以外にもSDGsやコロナウイルス関連などの流行のトピックが出題される可能性もあります。
ニュースや新聞などをチェックしておくと役に立ちます。
ここで重要なことは、
「文章を書くことが得意だから大丈夫!」という意識は捨ててください。
作文を書くのではなく、
小がつきますが、あくまで論文なのです。
しかも、採点基準は理解力・論理的考察力・記述力・表現力・主体性など、
様々な力です。

小論文では文章のうまさというよりも、
いかに論理的な説明ができているかということが問われます。
これはちゃんと練習していないと意外に難しいです。
自分1人ではよく書けていると思っていても、
実際にはそうなっていないというケースも多いです。
書いたらそのままにするのではなく、
必ず添削が必要なのです。
だからこそ、指導者が必要なのです。
また、小論文に関しては回数が必要です。
あまり差がないと思っている受験生があるかもしれませんが、
前期が終わってから、
きちんと対策が出来ているかどうかは、
雲泥の差です!
よって、前期試験の敗者復活戦のノリで受験をすれば、
まず不合格になります。
この気持ちは小論文に現れます。
そのような根性見え見えの小論文を書くのだけはやめましょう!
各大学の後期日程で求めている受験生に相応しい小論文を書く!
この本気が相手に伝わるのです。
具体的な指導の流れを、
新潟大学法学部を例を書かせて頂きます。
国立大学二次 小論文対策 サンプルスケジュール
【全体の流れ】
- 共通テスト終了(1/18・1/19)直後から本格的に二次小論文対策をスタート
- 5つのテーマに沿って小論文を書き、48時間以内の添削&アドバイスを受ける
- 添削内容をもとに自己修正 → 次のテーマへ
- 必要に応じて追加課題に挑戦(再添削も可能)
- 新潟大学法学部 前期試験(2/26) → 結果を踏まえ、後期に向けて再調整
- **新潟大学法学部 後期試験(3/12)**まで最終仕上げ
【1月20日~2月25日:前期試験(2/26)対策】
1月20日~1月26日:テーマ1
- 1/20-1/21
- テーマ1の課題文を読み込み、構成案・アウトライン作成
- 可能であれば他大学の小論文過去問や参考例文をチェック
- 1/22
- テーマ1の小論文を執筆(初稿) → 当塾に提出
- 1/23-1/24
- 48時間以内に返却される添削結果・アドバイスを確認
- 誤字脱字のチェックや表現改善のポイントを重点的に把握
- 1/25-1/26
- 自己修正(再提出はなし)
- 次のテーマの準備に入る
- ※余力があれば、追加課題に取り組み、もう一度添削を依頼可能
1月27日~2月2日:テーマ2
- 1/27-1/28
- テーマ2の課題分析、資料読み込み
- 1/29
- 小論文執筆(初稿) → 提出
- 1/30-1/31
- 添削結果確認 → 自己修正
- 2/1-2/2
- 必要に応じて追加課題へ挑戦
- 前期試験までの学習計画を再確認
2月3日~2月9日:テーマ3
- 2/3-2/4
- テーマ3の課題文をもとに構成案作成
- 2/5
- 小論文執筆(初稿) → 提出
- 2/6-2/7
- 添削結果の受取・確認
- 自己修正後は、ほかの教科の勉強との調整もしっかり行う
- 2/8-2/9
- 追加課題に取り組むか判断
- 他教科の仕上げも同時並行で進める
2月10日~2月16日:テーマ4
- 2/10-2/11
- テーマ4の課題分析、キーワード整理
- 2/12
- 小論文執筆(初稿) → 提出
- 2/13-2/14
- 添削結果確認 → 重要な指摘はノートにまとめ、再発防止
- 2/15-2/16
- 自己修正・表現力の強化
- 追加課題・他教科対策とのバランスを図る
2月17日~2月23日:テーマ5
- 2/17-2/18
- テーマ5の課題文を読み込み、まとめ作業
- 2/19
- 小論文執筆(初稿) → 提出
- 2/20-2/21
- 添削結果確認
- (余裕があれば)追加課題に再挑戦でさらにブラッシュアップ
- 2/22-2/23
- 自己修正&仕上げ
- ここで 5つの小論文全体の見直しを行い、共通する弱点を最終チェック
2月24日~2月25日:最終調整
- 2/24-2/25
- 前期試験直前の総復習
- 自分の書いた小論文を読み返し、頻出ミスや書き方のクセを再確認
- 2/26(前期試験)
- 新潟大学法学部 前期試験
【2月27日~3月11日:後期試験(3/12)対策】
※前期試験の結果発表や自己採点を踏まえつつ調整
2月27日~3月3日
- 前期試験の感触を整理し、必要であれば 再度小論文添削プランを短期集中で実施
- 追加課題や大学別の過去問演習を中心に、「弱点補強」に集中
3月4日~3月8日
- 小論文対策の総復習
- 前期対策で書いた5つのテーマや追加課題の添削ポイントを再チェック
- 改善点やよくあるミスをまとめた「自分専用マニュアル」を作る
3月9日~3月11日
- 後期試験直前の最終仕上げ
- 模擬小論文を書いてみる → セルフチェック
- 余裕があれば添削サービスへ再依頼(追加プラン)
- 他教科とのスケジュール調整も忘れずに
3月12日
- 新潟大学法学部 後期試験に臨む
このスケジュールをもとに、当塾の小論文対策プランでは「最短・最適な学習サイクル」を実現いたします。
合格につなげるために、ぜひ本格添削サービスをご活用ください!
- テーマごとの「書く→添削→修正→次のテーマ」サイクルを回すことで、短期間でも効率的に文章力を高める
- 添削は最短48時間で返却されるため、タイムロスを最小限に抑えて学習を継続
- 余力がある場合、随時「追加課題」に挑戦し、再度添削を受けることでさらに完成度UP
- 前期試験後も結果や手応えを見極めて、後期試験まで弱点を集中的に補強可能
【プランのポイント】
- テーマごとの「書く→添削→修正→次のテーマ」サイクルを回すことで、短期間でも効率的に文章力を高める
- 添削は最短48時間で返却されるため、タイムロスを最小限に抑えて学習を継続
- 余力がある場合、随時「追加課題」に挑戦し、再度添削を受けることでさらに完成度UP
- 前期試験後も結果や手応えを見極めて、後期試験まで弱点を集中的に補強可能
このスケジュールをもとに、当塾の小論文対策プランでは「最短・最適な学習サイクル」を実現いたします。
合格につなげるために、ぜひ本格添削サービスをご活用ください!
また、嚶鳴進学塾の添削例も挙げさせて頂きます。
新潟大学 法学部 前期 小論文
令和6年度 入学試験問題
【問題】
X 高校では、毎年の学園祭で、各クラス対抗の「演劇コンテスト」が行われており、各生徒がこのコンテストに向けて真剣に演劇に取り組んでいた。生徒の中にはそのコンテストに参加したいがために同校を志望した者もいたほどであり、年 Y 組もまた、コンテストで賞を取るために数か月以上前から、クラス全員で放課後夜遅くまで準備を行っていた。このコンテストは地域での評判も良く、例年、地域の住民もコンテストを観るためにつめかけるほど人気のイベントであった。
ところが、学園祭の1週間前、Y 組の生徒である A、B、C名が、演劇練習からの帰宅途中に立ち寄ったスーパーマーケットで、コンテストのための小道具(1,500円相当)を万引きしたとして警察に捕まった。初犯であり反省している等の事情から、A らはすぐに帰宅を許された。この事態を重く見た X 高校は、その翌日 Y 組の「演劇コンテスト」への出場を認めないとの処分を下した。これに対して、A、B、Cを除く Y 組の生徒全員が反発し、この処分を取り消すよう校長に詰め寄った。
以上の事実をもとに、高校側の処分の根拠と生徒側の主張の根拠をそれぞれ整理しなさい。そのうえで、あなたはどちらの立場を支持しますか。相手方への反論も含め1,000字以内で論じなさい。
【小論文】
X高校側の処分の根拠は、まず学校の規律と社会的信用を守ることにある。万引きという犯罪行為が生徒の一部から出た以上、学校としてはその行為を見過ごすことはできない。また、今回の万引きは「演劇コンテスト」のための小道具を盗んだものであり、学校行事に直結する問題であることから、事態の重大性は一層増す。そこで高校側は、学校の名誉や地域住民との信頼関係を維持するために、クラス全体に対して出場停止という厳しい処分を下し、ルール違反に対する強い警告の姿勢を示したと考えられる。
一方、生徒側の主張の根拠は、処分を受けるべきは万引きを行ったA・B・Cの3名のみであり、ほかのクラスメイトには直接の責任はないという点である。Y組の生徒たちはコンテストに向けて数か月以上も努力してきており、その成果を発表する機会を奪われるのは不当と感じるのも自然だ。加えて、本来であれば万引き行為に対しては個々の処分がなされるべきであり、クラス全員が処分されるのは「連帯責任」の範囲を超えた不当な処分だと捉えることができる。
私は、学校側の判断を支持したい。確かに、クラス全体が出場停止になるのは一見すると重すぎる処分のように感じられる。しかし、Y組の生徒は一丸となって演劇コンテストに取り組んできたという事情を踏まえると、このような結果に至る背景には、クラス全体が一種のチームとしての強い結束を持っていたことが大きい。だからこそ、仲間内の不正行為があれば、全員がその責任をある程度共有すべきという考え方も成り立つと思う。
また、生徒側が「A・B・Cだけを処分すればよい」と主張するのは分かるが、その場合、クラスが果たして万引き発覚後も正しく当事者をサポートし、再発防止に協力するかというと疑問が残る。学校側は厳しい措置を通じて、生徒全体に不正行為に対する連帯責任の意識を持たせたいのではないか。その狙い自体は、将来社会に出るうえで重要な規範意識の形成につながると考える。
以上の点から私は学校側の処分を支持する。しかし、処分後にクラス全体で対話の場を設け、なぜ万引きをしてはいけないのかを改めて確認し合うプロセスも必要である。そうした振り返りによって、今回の出場停止という厳しい処分が単なる罰にとどまらず、生徒の成長に資する教訓となることを期待したい。
【採点/添削】
《論旨の明確化》 4/10
設問の求める「高校側の処分の根拠」と「生徒側の主張の根拠」が整理されてはいるものの、両者の対比がやや淡白であり、深く踏み込んでいない印象です。序論や結論で「自分が何を主張したいのか」をさらに明確に提示すると、読者にとって分かりやすくなるでしょう。
《構成・論の流れ》 5/10
序論・本論・結論の形は保たれていますが、それぞれの段落で何を論じているのかをもう少し明確に示しておくとベターです。特に序論で問題提起を、結論で主張の要約をより意識して書くと、論の流れが整理されて読みやすくなります。
《内容の深掘り》 5/10
「学校側の処分の意義」「生徒側の反発の根拠」の双方を示してはいますが、万引きという法的・社会的問題や、教育の観点から見た連帯責任の是非など、もう一段深い考察があるとさらに説得力が増します。
《論理的整合性・一貫性》 6/10
大きな矛盾や飛躍は見当たりませんが、「なぜ学校側の厳しい処分が必要なのか」「なぜ個別処分では不十分なのか」を論理的につなげる説明があれば、より一貫性が高まります。反対意見への応答としては、連帯責任を課す教育的効果についてもう少し具体的な説明があると良いでしょう。
《語彙力・表現力》 5/10
比較的読みやすい文章ですが、「〜と考えられる」「〜と言える」など、断定を避ける語句が多用される傾向があります。自分の主張をもう少し力強く述べるためにも、必要な部分では「〜すべきだ」といった明確な表現を用いてみましょう。
《独自性・オリジナリティ》 5/10
双方の立場を整理し、学校側を支持する結論を導いていますが、一般的な議論の範囲にとどまっています。「クラスの連帯感を逆手にとって、どのように再発防止につなげるか」など、プラスアルファの具体的な提案があると独自性が高まるでしょう。
《誤字脱字・文法チェック》 7/10
明らかな誤字脱字は少なく、文体の統一も比較的保たれています。ただし、段落途中で読点(、)が少なく、やや読みにくい箇所があります。長めの文が続くところでは句点(。)や読点(、)を工夫し、よりスムーズに読めるようにしましょう。
《結論の明確化・まとめ》 5/10
結論として学校側の処分を支持する立場を明示していますが、その根拠が本論部分と完全には結びついていない印象です。結論で「本論の要約」を示し、そこから「だからこそ学校側の処分を支持する」と繋ぐように書くと、より締まりが生まれます。
《字数・文字数制限の遵守》 8/10
全体的にまとまりはありますが、指定された1,000字以内には収まっていても、やや駆け足でまとめている箇所があります。序論・本論・結論の配分をもう少し意識し、論じたい部分に十分な字数を割くことを意識しましょう。
《読後の印象・説得力》 6/10
読み終わってから「なるほど」と思わせるだけの意義は感じられますが、処分を支持する判断に至るまでの説得力をさらに高める工夫がほしいところです。たとえば「教育現場における懲戒の意義」「社会全体へのインパクト」などをもう少し深く論じれば、読後感は格段に良くなるでしょう。
《総合点》 56/100
【総評】
テーマの要点はそれなりに整理できており、クラス全体への処分を支持する意見を結論としてまとめています。しかしながら、両者の主張をもう少し具体的に分析して、自分なりの考えを論理的に展開する工夫があるとさらに評価を伸ばすことができます。単なる一般論で終わらず、「なぜそう考えるのか」をより明確に示し、結論と本論をしっかりと結びつけてみてください。「このままではやや説得力不足」と感じられる点を自覚し、次回に向けて論証や構成の工夫を重ねることを期待しています。
【表記の正確性】
以下は、元の【小論文】から読みやすさ・表記ゆれ等を中心にピックアップした箇所です(いずれも誤りというほどではありませんが、
修正するとより明快になります)。
- 「そこで高校側は、その翌日 Y 組の『演劇コンテスト』への出場を認めないとの処分を下した。」
- 修正案:「そこで、高校側はその翌日、Y組の『演劇コンテスト』への出場を認めないとの処分を下した。」
- 理由:文頭に「そこで、」と読点を加えることで文の区切りをはっきりさせ、読み手が文脈を把握しやすくなります。
- 「Y組の生徒たちはコンテストに向けて数か月以上も努力してきており、その成果を発表する機会を奪われるのは不当と感じるのも自然だ。」
- 修正案:「Y組の生徒たちは、数か月以上にわたりコンテストの準備を重ねてきたため、その成果を発表する機会を奪われるのは不当だと感じるのも当然だ。」
- 理由:「努力してきており〜感じるのも自然だ」という表現を、より簡潔かつ力強い言い回しに変更。読みやすさが向上します。
- 「だからこそ、仲間内の不正行為があれば、全員がその責任をある程度共有すべきという考え方も成り立つと思う。」
- 修正案:「だからこそ、仲間内の不正行為が明るみに出た場合には、全員がその責任を共有する必要があるという考え方も成り立つと言えよう。」
- 理由:ややあいまいだった表現を「明るみに出た場合には」と具体化し、「共有する必要がある」と明確な語調にすることで文章の力強さを増しています。
- 「学校側は厳しい措置を通じて、生徒全体に不正行為に対する連帯責任の意識を持たせたいのではないか。」
- 修正案:「学校側は厳しい措置を通じて、生徒全体に“不正行為は自分にも影響を及ぼす”という連帯責任の意識を浸透させたいのだろう。」
- 理由:「持たせたいのではないか」という推測的な書き方から、もう少し踏み込んだ表現をすることで、文章に厚みをもたせています。
- 「以上の点から私は学校側の処分を支持する。」
- 修正案:「以上の点を踏まえ、私は学校側の処分を支持する。」
- 理由:「以上の点から」「〜私は」と続くよりも、「以上の点を踏まえ」のほうが接続語として自然であり、まとめの印象がより強まります。
【このテーマの基礎知識】
- 懲戒処分と教育的指導の違い
学校での処分には、「懲戒処分」と「教育的指導」の二つがあります。前者は違反行為に対する制裁的意味合いが強く、後者は生徒を正しい道に導くための指導が主眼です。本事例では「出場停止」が懲戒的意味合いを持っており、教育的効果とのバランスが問題となります。 - 連帯責任の背景
部活動やクラス活動でよく取り上げられる「連帯責任」は、日本の学校文化として根付いている面があります。一方で、「個々のミスを全体で背負うのは不合理」という反対意見もあり、その是非はしばしば議論の的になります。 - 万引きの社会的影響
万引きは窃盗罪にあたり、れっきとした犯罪行為です。未成年の場合、家裁送致などになる可能性もあり、学校だけでなく社会全体からの厳しい視線が向けられます。学校の評判や地域からの信頼が損なわれるという懸念から、厳正な処分がなされやすい側面があります。 - 教育現場における権威と信頼
教育機関は地域社会からの信頼を得て成り立っています。今回のような事件が起こると、「学校の管理責任」「教員の指導不足」などの非難が及ぶ可能性もあり、学校側が厳しい姿勢を取るのはこうしたリスクを回避する意味合いもあります。 - 再発防止と更生
懲罰の目的の一つは再発を防ぐことですが、ともすれば懲罰だけでは解決しきれない場合が多いです。今回の事例では、万引きの根本的な理由を把握し、クラス全体でサポートや話し合いを進める教育的アプローチが、より効果的な再発防止につながる可能性があります。
【小論文の書き方】
- 序論でテーマを提示
- 問題文の概要を簡潔にまとめ、「学校側の処分の根拠」と「生徒側の主張の根拠」を整理する。
- 「なぜこれが問題となっているのか」を読者に示し、論じる意義を明確化する。
- 本論で対立する主張を深堀り
- 高校側の視点(学校の名誉維持、再発防止、社会的影響など)
- 生徒側の視点(個人の責任、長期的準備の努力、教育的配慮など)
- 自分がどちらの立場を支持するか、背景や具体例を挙げて論証する。反対意見への応答も盛り込むことで説得力が増す。
- 結論で立場の再確認と課題提示
- 本論の議論をまとめ、最終的な結論をはっきり書く。
- 処分の是非だけでなく「再発防止策」「教育的意義」など、今後の展望や提案を入れると深みが増す。
- 字数と文体のチェック
- 1,000字以内なら、序論・本論・結論の配分をだいたい2:5:3程度で考える。
- 文体は「だ・である調」か「です・ます調」に統一し、誤字脱字がないか念入りに推敲する。
- 多面的な視点を忘れない
- 連帯責任の功罪、万引きの重み、教育的配慮の重要性など、できるだけ多角的に論じ、最終的に自分の立場を際立たせる。
【参考例文】
X高校における「演劇コンテスト」に向けたY組の熱心な取り組みは、学生生活の醍醐味を象徴している。しかし、その準備過程でA・B・Cの3名が万引きを犯したことで、学校側はY組全体の出場を禁止し、生徒側は猛反発している。本件を考えるうえで重要なのは、学校側・生徒側の主張がいずれも一定の合理性を持ち、それぞれが教育の意義をどう捉えているかにかかっている点である。
まず学校側は、懲戒処分を通じて校内の規律と社会的信用を守ろうとしている。万引きは犯罪であり、しかも学校行事の準備に関連する行為であった以上、見過ごすことはできないだろう。地域住民の注目を集めるコンテストであればなおさら、学校が毅然とした態度をとることで、「ルール違反は重大な結果を伴う」というメッセージを発信する意図がうかがえる。さらに、チームとして強い結束を誇るY組に対して一律の処分を下すことで、不正が発覚した際には全体で連帯責任を負う必要があると強調していると考えられる。
一方、生徒側の反論は、直接の加害者である3名と、それ以外のクラスメイトの区別を求めるものだ。数か月にわたり必死に練習を重ねてきた成果を、一部の不正行為によって奪われるのは不当という主張である。また、個別の処分で足りるはずのところをクラス全体にまで拡大することは、処分の範囲を越えているとも指摘できる。そのうえで本来、学校は間違いを犯した生徒の更生を手助けし、再発防止につなげる役割を果たすべきではないかという見解を示す。
私は、学校の懲戒方針を一定程度理解しつつも、今回のような一律の出場禁止という措置は「教育的配慮」の観点から再考の余地があると考える。連帯責任を促すことで生徒の規範意識を高める効果は認められるが、同時に個々の努力が不当に扱われるリスクや、万引きをした当事者への適切な指導機会を損ねる懸念もある。そこで、私は学校側には厳格な対応とともに、クラス全体が対話を通じて問題を共有し、再発防止策を話し合う場の設定など、教育的アプローチを並行して行うことを提案したい。
以上を踏まえて、処分の必要性を否定するわけではないが、懲戒と教育のバランスをどう確保するかこそが、今回の問題の本質である。「制裁」だけでは生徒の成長に繋がりにくい。万引きの重さを認識させると同時に、一人ひとりが公正な評価を受けられる道筋を探ることが、今後の高校教育の大きな課題であるといえる。
【採点者からのメッセージ】
まずはここまで書き上げたこと、お疲れさまでした。文章には「物事を多面的に捉えようとする姿勢」が感じられ、十分に努力が伝わってきます。「失敗を正しく認め、同時に活かす」という一節を残した哲学者・中江藤樹のように、失敗や課題は未来の成長の糧ともなるはずです。
今回の小論文で意識してほしいのは、読み手となる採点者が「この意見には筋が通っている」と納得できるように、序論・本論・結論を三段階に分けて書き進めることです。特に実際に手書きする際は、一段落ごとに要点を簡単にメモしてから文章化すると、余計な脱線や行き当たりばったりの展開を防ぎやすくなります。また、用紙が限られている場合は字数を意識しすぎて内容を圧縮しないよう、必要な部分にはしっかり文字数を割き、論を深めてみてください。
最後に、受験は時に大きなプレッシャーを伴いますが、「今やっている努力は必ずどこかで報われる」と信じて踏ん張ってください。さらに良い文章へとブラッシュアップできることを期待しています。応援しています。頑張ってください!
嚶鳴進学塾では、
本気で後期試験に合格をしたい受験生を全力で応援します!
大逆転のチャンスですので、
特別特典をご用意いたしました!
講座内容は以下の通りです。
【大逆転合格!国立大学後期試験 小論文対策講座】
・内容:志望大学の過去問もしくは類似のテーマを5テーマ指導
・指導方法:オンラインでの添削指導(全国対応)
・期間:申し込み日から受験前日まで
・特典:
①講座受講期間中は回数無制限での添削
②講座受講期間中は回数無制限での質問可能(LINEもしくはメール)
③講座受講期間中、最低3回のZOOMによる個別相談
④面接練習が必要な場合は要相談
・受講料:19,8000円(税込) → 特別応援受講料 166,000円(税込)
(教材費込み)
*まずは、お気軽に無料相談も可能です。
お申込み、ご相談、無料体験へのお問合せは、
以下のフォームからお願い致します。
「お問合せ内容」の部分に、
「国立大学後期 小論文対策講座」とご記入頂ければ助かります。
国立大学後期小論文対策講座以外での
大学入試の小論文対策についても、
お問合せは可能です。
↓