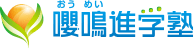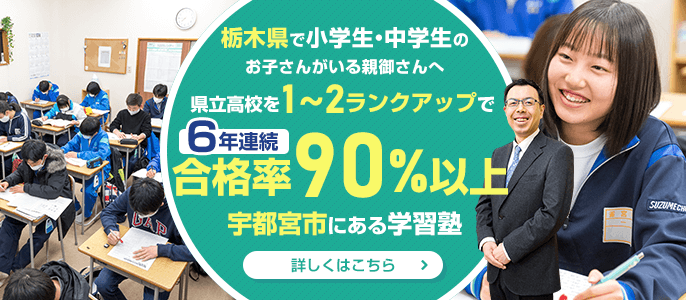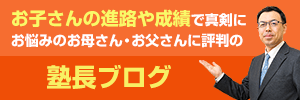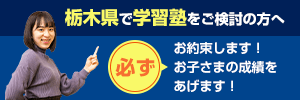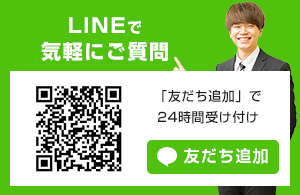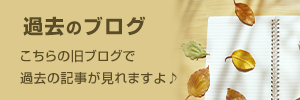続きの続きです。
今日は、数学についてです。
試験に出る確率が高い分野を重点的にやり、
そうでないものはやらない徹底的な割り切りが、
直前には大切になります。
でも、今はダメですよ!
全てをやりましょう!!
ただし、理科社会はヤマを張りにくいです。
各分野まんべんなく出題されるので、
「ここが出る!」と直前に断定するのは避けたいですね。
出そうな分野をチョイスして重点的にやるより、
すべての分野をくまなく押さえておきたい。
ルーレットの一点賭けは怖いのです。
よく大手塾が「予想問題的中」とあるのは、
中学3年間の膨大な量のテキストやテストを配布していれば何かが当たるわけで、
ノストラダムスの大予言みたいなものであてにはならない。
だからこそ、嚶鳴進学塾も大手塾並の演習を行っております。
しかし、数学は予測が立てやすいのです。
栃木県の数学は、関数が大きな配点を占める。
関数が出ない年はない。
これは全国的傾向でもあります。
というか、関数抜きでは数学の問題が作れないのです!
関数はいったんコツを知ったらコンスタントな得点源になります。
逆に、図形は難問にぶつかったら解法がひらめかずお手上げだし、
証明問題でまごついていたら大変です。
2か月というタイムリミットを考えれば、
一番出題され、
慣れたら確実に点が取れる関数に勉強の比重をおくのは必然と言えます☆
関数が苦手な受験生はまず、
塾のテキストや学校の教科書を復習するべきです。
新しいテキストに手を出してはいけません。
一度やった教科書やテキストには、
どれだけ過去に授業を受けたとき真剣に聞かなかったとしても、
記憶の残滓くらいは残っている。
教科書やテキストを引っ張り出して復習するのが最優先です。
新しいテキストは一番風呂のように体になじまない。
あと一次関数・二次関数だけでなく、
中1で習った反比例を忘れてはなりません。
反比例は意外にウイークポイントで、
双曲線のグラフに苦手意識を持っている受験生は多いです。
反比例は死角になりやすいので気を配りたいですね。
また、関数の難問には相似が絡みます。
グラフ内の面積比を求める問題は相似の知識が必要です。
関数と相似を同時並行で基礎を押さえるべきです。
基礎力がついたと判断したら、
過去問に徹底的に当たります。
栃木県の過去問だけでなく、
旺文社の「全国高校入試問題正解・数学」を買い、
関数の問題に片端から当たってみる!
ここで注意してほしいのは、
絶対に過去問は新しい方がいい。
古くさい市販の問題集は使ってはならない。
強い効果があるのは過去3年の新しい過去問に限ります。
私が「栃木県の過去問を10年分解いた!」と言う事に、
うん?となるのは、これが理由です。
野菜と同じで過去問は新鮮なほどおいしく、
ウサギの飼育小屋に散らばるキャベツの屑のような古い問題を解いても効果は薄いのです。
関数は絶対出題される分野だが、
絶対出題されるからこそ出題者は頭を使い、
入試問題は年々進化しているのです。
新しい過去問を解けば、
既存の問題とは思ってもいない角度から突いてくるのが分かります。
古い過去問は結構あちこちで使い回しされていて、
惰性で解けてしまいます。
本番の入試問題はパリパリの新作です☆
どんなアプローチで問われても対応できるよう、
新作慣れする目的で新しい過去問を解きまくることです。
関数を勉強すると意外な副作用があります。
それは、頭の中が整理整頓されることです。
関数とは段取りの学問で、
一つ一つ適切な段取りを重ねていけば解けます。
これは数学の他の分野、また他教科にも波及します。
関数が高校受験で配点が高いのは、
高校側が整理整頓された論理的な思考ができる受験生を
入学させたいという意思の表れでもある。
とにかく、確実に出題され配点が高く、
また得点が安定しやすい関数に時間をかけるのが直前の鉄則です!
嚶鳴進学塾のアメブロはこちらです♪
↓
【12月の休校日】
12月5日(日)・12日(日)・19日(日)
12月31日(金)
*12月は冬期講習日程となりますので、個々人により異なる場合もございます。
詳しくは、冬期講習の日程表をご確認ください。